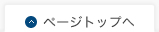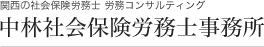先の通常国会で年金法が改正されました。いつもと違ってほとんど話題にならなかった印象がありますので、国民のどの程度の人が関心を持っているのか疑問ですが結構大きな改正でした。
これは、「税と社会保障の一体改革」という名のもとに行われたため、消費税の成立アップという話題の中に隠れてしまい人々の関心を呼ばなかったのかもしれません。
改正点の主なものは以下の6つです
1.受給資格期間の短縮(平成27年10月1日から)
現在の受給資格期間は25年間ですが、これが10年に短縮されます。現在受給資格期間が25年間に足りないため無年金となっている高齢者に対しても10年間資格期間を満たしている人に対しては、保険料納付済み期間に応じて年金が支給されます。
2.基礎年金国庫負担分2分の1の恒久化(平成26年4月から)
現在はあちこちからお金をかき集めて(ここ2年ほどは赤字国債によって)2分の1を維持していますがそのかき集めている部分に消費税が当てられます。
3.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大(平成28年10月から)
以下の条件に適合する人に対して厚生年金・健康保険の適用が実施されます。
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③ 勤続期間1年以上
④ 従業員501人以上の企業の労働者
4.産休期間中の厚生年金・健康保険の保険料の免除(2年を超えない範囲内で政令で定める日から)
現在は育児休業期間中だけ認められている厚生年金・健康保険の保険料の免除が、産前産後休業期間中まで拡大されます。
5.遺族基礎年金の父子家庭への支給開始(平成26年4月から)
現在、遺族基礎年金は子のある母(いわゆる母子家庭)にしか支給されてきませんでしたが、父子家庭にも支給されるようになります。
6.低所得者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる(2年を超えない範囲内で政令で定める日から)
受給資格期間を満たしていても年金額が少額な低所得者や障害者等に対して一定の上乗せ給付を実施するというものです。
そのほかにも、「所在不明高齢者に係る届出義務化」、「国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への参入」、「未支給年金の請求範囲の拡大」等々細かいところも含めれば多岐にわたる改正が実施されました。