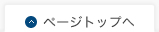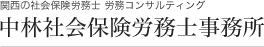中小零細企業では、社会保険料が高くつくため、始めから会社を厚生年金・健康保険の適用事業所としていない、適用事業所としていたが全喪の手続きをして適用事業所とならなくした、被保険者を限定したものだけにして多くの人の届出をせず被保険者としていない、等々の方法により経費を切り詰めておられるところが見受けられます。
そのことの是非(当然違法ですが)をここでは申し述べませんが、厚生年金・健康保険の適用を受けてない人は国民年金・国民健康保険に加入することになるのですが、その保険料を未払い滞納している人が非常に多いことが問題になっています。特に20歳台の滞納率がほぼ50パーセントに及んでいます。
滞納の一番大きな理由は「所得が少なくて払えない」ということですが、国民健康保険は保険証がないと医療機関で医療を受けたときに一番痛みがあるので別の問題で深刻なのですが、ここでは、国民年金の保険料の滞納の話です。
特に若い人には誤解があって、「年金制度に入ってない」という人が結構たくさんいます。日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は強制加入なので「入りたくない」は通用せず、全員加入しているけど保険料を滞納しているということになっているのが本当のところです。
所得があるにもかかわらず、意識的に保険料を滞納している人の最大の理由は、「将来年金は貰えない」(と思い込んでいる)と「老後は自助努力で何とかする」です。確かに老後は恐らく自助努力の必要性は出てくると思います。少子高齢化で高齢者の支え手が、現在より少なくなるため支給額あるいは現役世代の所得の何パーセントもらえるかという支給率等がこれから下がっていく可能性があるからです。
しかし、将来年金は貰えないのかどうか、払った保険料分は返ってくるのかどうか、ですが、賦課方式の制度が続く限り返ってくる設計になっています。ちなみに、現在の1ヶ月の保険料(13,300円)を20歳から60歳まで40年間かけると、13,300円×480ヶ月=6,384,000円、年間の年金額は現在797,000円ですから6,384,000円を797,000円で割ると、約8年で元が取れる計算になります。支給開始年齢が65歳なので73歳まで生きれば完全に元を取ったことになります。金利を考慮していないのは、金利が上がるということは物価が上がるということで、年金の支給額は原則として物価スライドが考慮されているためです。
以上のように「年金」という名称から老齢年金ばかりクローズアップされていますが、年金には別に「障害年金」と「遺族年金」があります。若い人にとって老齢は将来必ず来るもので、また支給まで時間がかなりあるため自助努力を考える余裕が在りますが、事故や病気などは予測がつきません。
いずれも支給要件として、保険料の滞納がないことが条件になっていて、まさかのときに医療は全額自己負担、障害が残れば収入がなくなるといったケースが十分起こりうる可能性があります。初診日(はじめて治療を受けて傷病が確定した日)の前日までに被保険者期間がある場合は、そのうち3分の2以上が保険料納付済み期間と保険料免除期間でなければ受給資格がありません。
例えば、大学生のときに国民年金の保険料を納付せず、卒業後厚生年金の適用事業所に勤務した場合、4年以内に事故に遭って、障害が残った場合障害基礎年金と障害厚生年金が支給されません。また、長くフリーターをしていてずっと保険料を滞納している場合も同様です。
ですから、学生のときは、収入がなければ「学生の納付特例」を利用して免除にしておくこと、また収入がない場合は、「保険料全額免除制度」や「保険料半額免除制度」を利用しておく必要があります。免除にしますと、老齢基礎年金は減額になりますが、40年間全部保険料全額免除していても、(税金投入分の3分の)1は支給されますし、「障害」「遺族」は通常通り支給されます。
パートタイム労働者といっても、就労時間がいわゆる正社員とほとんど同じで勤務していても、パートと呼ばれている人もいて、正社員との境目がますますなくなってきています。
法律上(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条)では、「通常の労働者と比し、所定労働時間の短い者」と定義されていますがその勤務時間等の内容は様々です。パート労働法以外の法律上の取り扱いはさまざまですので一概に言えませんが、一つの基準として、週の所定労働時が、30時間と20時間という区切りがあります。
ただ、勤務時間が短いとはいえ募集・採用・就労にあっては、その手続が正社員とほぼ同じことが必要な場合が多く注意が必要になります。
労働条件の明示・雇用期間の定め(定めない場合は期間雇用となりません)などは必ず行わなければなりません。また、各法律も正社員とパートの区別のあるなしがありますので、一つの事業所の中にいろいろな雇用形態の従業員が混在している場合は、それぞれの雇用形態に応じたルールを定めておいたほうがいいでしょう。
具体的には、それぞれの雇用形態ごとに就業規則を定めるか、一つの就業規則で必要事項ごとに適用範囲を区分するかです。正社員にだけ就業規則を作り適用範囲を定めてないと、パートであってもほとんどの部分が適用になってしまいます。何も定めていないと法律で除外されている(たとえば社会保険・労働保険の適用範囲)ほかは適用(たとえば育児介護休業などが)になってしまいます。また雇用形態ごとに別々に就業規則を作成していても、労働基準法上は一つの就業規則となりますので、作成した時期が離れていてもすべて届出が必要になります。
最近はサービス業を中心にパート社員の構成比率が年々上昇していますが、正社員を廃止して、「全員時間給社員にしてしまう」という発想もあります。例えば、月給30万円の正社員に時給換算して見ますと、月平均勤務日数が20.4日(完全週休2日制の場合)で、1日の所定労働時間を8時間とすると、30万円÷20.4÷8=1,838円(賞与除く)になります。一般事務の派遣料が1時間当たり1,700円~1,800円ですから、果たして高いのか安いのか(勿論法定福利費等は除いています)、その判断は分かれると思いますが、パートがいいのか正社員がいいのかあるいは違いがないのか、雇用をしっかり守れば案外時給社員もよろしいのではないでしょうか。
労働条件の変更で会社の事業内容・仕事の業務内容が変わることによる人事異動・配置転換の問題はどの会社でも起こりうる問題です。
その場合の会社側の対応と従業員個々の対応について、裁判になった事例も結構あり、また裁判に至らなくても行政の相談所に持ち込まれたり、当事者同士で話し合われたりしていることも相当な数が存在しています。
会社側の対応として最低限必要なことは、あらかじめルールを決めておくということです。つまり就業規則に、会社の事情で各従業員の個別事情に配慮するとしても、人事異動・出向・配置転換はあり、業務の都合上行われる措置に従わなければならないと規定しておく必要があります。
特に、事業方針・経営判断については企画立案実施の決定がなされるのは、事業主または経営担当者の専管事項ですから、決定に至るプロセス上で従業員に対して意見を聞くことがあったとしても、実施が決定されてしまうと、その内容が公序良俗に反しない且つ企業経営上合理的に必要であれば従業員としては従う義務があるということになります。例えば、ニュースの中で取上げられている業務のIT化や新規事業に打って出るといった事例は普通にあることです。
勿論、IT化等は比較的年齢が高い層には拒否反応を示す人もありますが、十分な教育訓練を実施する、その業務を実施するにはそのスキルが全員に必要という理由があれば、それに対応できない人は自ずと他の場所に移ってもらうということは許容されることになります。
ただし、すぐに解雇するということはまた別の問題になってきます。十分教育したが当人の事情によりスキルアップが期待するほど伸びない、配置転換に適した職種が会社の中にはない、配置転換をしたがその職種の平均的な給料は配置転換される人の給料より安いので給料を下げた、配置転換をした所で反抗的な態度をとり他の従業員の職務の遂行に悪影響が出るなどの事情が出てくれば、基本的に普通解雇は許容されることになります。
もう一つよくある事例で、「業務遂行能力が他の人に比べて著しく低いので辞めさせたい」というケースです。この事例は個別判断によって解釈がいろいろあります。
まず、入社の条件としてある一定以上の、または特殊な能力を必要とする場合です。例としては、経理事務要員の責任者を募集する場合、会社として事務処理能力のほかに管理能力等に一定の水準を設けるはずです。その水準は他の一般事務要員と比べて当然違っているはずですし、また給与水準に差をつけている会社も多いと思います。このような場合は、合理的に見てその水準にあるかないかはすぐに判定が可能でしょう。そのときは職種の変更(一般事務)する余裕が会社にあればまずそのような手を打つことが第一ですが、もともと経理事務のポストが一つしかなく、他の一般事務も一人とか二人しか必要ない場合で、そこには欠員がないときは、解雇もやむをえないといえます。
また、端的な例で実際に裁判例になっている話ですが、営業部長を人材紹介会社(いわゆるヘッドハンティングの会社)から紹介を受けて雇用したケースで、成績が上がらなかったため、解雇して裁判で争われ、その解雇が有効とされました。
つまり、採用の条件がはっきりしていて一般的に見て相当高い能力が必要とされる職種や人材の場合は解雇をしても比較的許容されることが多いようです。ですから誰でもできる仕事で高い能力も必要のない業務であれば、仕事ができないという理由だけでは解雇が少し難しくなります。
少し前からサービス残業が話題になっています。ここ最近では、全国の労働基準監督署がサービス残業の撲滅を目指して、積極的に摘発を行っています。
また、厚生労働省からサービス残業を摘発され従業員に対して支払った数字が公表されています。100万円以上支払った企業数と金額ですが、大阪府の場合、平成14年度で、52企業で総額約8億4千万円に上っています。また、平成13年度の場合は、それぞれ27企業で約5億8千万円となっていまして、企業数・金額とも大幅に増えています。
特に大阪府の管轄労働基準監督署では、「サービス残業撲滅キャンペーン」と銘打って徹底した摘発に乗り出していますので、企業数・金額とも今年度も増加しそうです。その方法は、夜遅くまで明かりがついている事業所に目星をつけて、何回か確認したうえで、その事業所に立ち入りし、出勤簿・タイムカード等をチェックし、それを賃金台帳と比較して割り出していくようです。
特に、象徴的な事件としてサラ金の武富士が数億円に上る残業に掛かる未払い賃金を支払うよう是正勧告を受けたのは、記憶に新しいことです。
一般的に労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間を超えて働かしてはならない(労基法第32条)、と定めています。その時間数を超えて時間外労働を行わせるには、就業規則には業務上やむを得ない場合には時間外労働を行わせる旨定め、尚且つ過半数組合または従業員の過半数を代表するものとの書面による協定を締結し、それを所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。しかし、休日・時間外労働の協定も、無制限に残業を認めているわけでなく、1日4時間、1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間、1ヶ月45時間、2ヶ月81時間、3ヶ月120時間、1年間360時間とそれぞれの期間の上限の時間が定められています(労働基準法第36条の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)。ですから、その上限を超えると勿論違法になりますから、その上限を超えた労使協定は無効になり、所轄労働基準監督署で受け付けてもらえません(特別条項付きの36協定という方法がありますが)。
ところが、労働基準法に休日労働と時間外労働の規制が及ばないものとして、管理監督の地位にあるものと機密の事務を取り扱うもの等が指定されています。これの主な対象は、管理監督の地位にあるものとは、事業主・役員・管理職を想定し、機密の事務を取り扱うものとは、役員以上についている秘書のことです。
そこで対策としてよく行われるのは、支払う給料を月給制にして役職名をつけて全員管理職にする、または支払う給料の中に休日出勤手当てと残業代を含んでいるという解釈をするという方法です。しかし、管理監督者の定義は、従業員に対する業務指揮権や人事権を持っていてその責任を負うもの、となっていますから部長職以上、少なくとも大企業の課長以上がそれに該当するとされています。しかも名称ではなく実態として行われていなければならないとなっていますので、課長と名称がついていても部下がいなかったり、上司の業務の指示を受けないと業務を行う権限がないものは管理監督者とはされません。勿論ルーチンワークを指示なく行っているというケースも管理監督者とは認められません。
そこで、業種・職種によっては、変形労働時間制を採用することによって時間外労働に対する割増賃金を削減できるケースもあります。
変形労働時間制は、
1.1ヶ月単位の変形労働時間制
2.フレックスタイム制
3.1年単位の変形労働時間制
4.1週間単位の非定型的変形労働時間制の4形態があります。
これはサービス業や製造業などで、1週間、1ヶ月、または1年の間に、あるいは季節ごとに業務の繁閑がある業種に有効です。また事務職でも繁閑がある部門では有効に取り入れることが可能です。
それぞれの変形労働時間制は導入しやすかったり、使いにくかったりしますし、また業種・規模によって採用できない変形労働時間制もありますので一度ご相談下さい。
厚生年金の支給開始年齢の引上げが昨年の4月から開始しているのはご存知のことと思います。
昭和16年4月2日以降生れの方は実質2年ごとに定額部分の支給開始年齢が1歳ずつ上がっていきます。最終的には、男性で昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生れの方は65歳にならないと年金が支給されません。
しかし、年金財政がだんだん逼迫してきつつあるため、年金の支給開始年齢を引き上げ、また支給補償額を平均賃金額の約52%(現在約60%)にしていくとしています。つまり公的年金だけでは老後の生活が豊かには過ごしえなくなってきます。
そんな中で、国の方針として老後の生活資金に対して「自己責任」と言い始めています。またそれに伴って、国の施策として60歳を超えて65歳ぐらいまで、できるだけ働けるようにしようとしています。そのもっとも顕著なものは定年の引上げです。現在、定年年齢を定める場合は、60歳を下回ってはならない(高年齢者雇用安定法第8条)、と定められています。それを65歳に法律で定めるまたはそのように政策を誘導していくことにしています。
しかし、最近の経済情勢からいっても、賃金額の比較的高い中高齢者を雇用していくことは非常に困難となっています。ちょうど50歳台の半ばくらいの年齢は団塊の世代と呼ばれ会社の年代構成のなかでも一番人数が多い世代になっている場合が多いと言われています。その年代が今後数年の間にどんどん定年を迎えますと、会社にとっても、本人にとってもなかなか難しい問題が多くなっています。
ひとつは、老後の生活費(主に公的年金の話)の問題ですし、もうひとつは退職金の話です。
税制適格年金は今後8年以内に廃止する、または他の退職金制度(退職年金制度)に移行しなければなりませんし、実際に定年退職者が多く発生するということは、それだけ現金が会社から出て行くということにほかなりません。
そのための支給原資をどう確保するかという話はまたの機会に譲るとしまして、定年の延長という話は、具体的な解決策のひとつとなり得ます。勿論、役職や給料をそのままにして延長するのではありません。また、会社の人員構成の高齢者がますます多くなってしまうという状況をそのままにするのでもありません。そこは一工夫二工夫をして給料総額を増やさず、わずかでも減らしてという方法が大原則になります。
特に製造業などでは、中高齢者が多く若年労働者が少ないという現象は、技術の継承という面からも大変問題があります。最近では、20歳台の5人に1人は職がないといわれていますし、中高齢者の雇用の確保の優先のしわ寄せが若い人に来ているともいわれています。
賃金総額をなるべく減らし、会社の人員構成もなるべく偏らせず技術の継承を図る、このような対策のひとつに、定年の延長は使えるひとつの選択肢になりえると思います。
過労による健康障害を予防するための疲労蓄積を自分自身で判定するためのチェックリストが厚生労働省より公開されています。
最近、過労死が労災と認定されるケースが増えてきています。それは昨年に、労災認定の基準が緩和されたことによることと、経営悪化に伴うリストラによって人員が減少しても仕事自体が少なくなったわけではないので、一人当たりの仕事量が増えていることにも原因があります。
従業員の中から過労死を出しますと、直接的な費用は労災保険の適用事業所で労災認定を受ければ保険から支給されますが、事業主には使用者としての安全配慮義務違反として逸失利益を損害賠償という形で、また慰謝料として支払う義務が課せられる場合があります。
そのための費用を確保するための話はまたの機会に譲るとして、事業主には労働時間が長時間にならないように、労働者の勤務時間を把握し、多い場合には改善策を実施する義務が法的に課せられています。
勿論長時間労働に強い人弱い人、ストレスにも強い人弱い人があり一様ではありませんが、そのためのひとつの判断材料として、そのチェックリストは使えます。
気をつけなければならないのは、長時間労働やストレスに対して、強い人弱い人ありますが、裁判になったときに基準とされるのは(判決では普通の人といっていますが実質的に)「弱い人」です。
賃金を年俸制で決めている場合でも、所定時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてもいけない、との判決が最高裁判所で出されました。会社側の主張は『年俸の中に割増賃金が含まれている』ということでしたが、その具体的な時間数や金額が明記されていなかったことが敗因です。 労働基準法で時間外の割増賃金を支払わなくてもよい場合は、以下の業務に限られます(労基法第41条、いわゆる第37条の適用除外者)。 1.第一次産業の従事者(林業を除く) 2.管理職または監督の地位にある者 どこからが管理・監督の地位にあるかの判断は、基本的に労働時間管理(出勤管理を含む)が自分でできる人・業務の指揮命令権を持っている人な どということになり、一般的には比較的規模の大きい会社の課長以上がその立場にあるとされています。ですから、『当社は主任職以上は管理職だ』 といっても実質的に業務の指揮命令権などが実際になければ認められません。基本的に管理職と管理監督者は違います。 3.機密の事務を取り扱う者 一般的には、秘書等のことを指します。 4.監視または断続的業務に従事する者であって、労働基準監督署の許可を受けた者 交通の監視・車両誘導・プラント等の計器類の監視など、精神的緊張の高い業務に従事する者や危険または有害な場所で業務を行う者については許 可されません。具体的には、宿直や日直などの業務がこれに該当します。 そのほかに、法律には明記されていませんが、今一部で静かなブームになりつつある、請負社員なんかは対象外になります。請負社員とは、もともとサラリーマンの必要経費の控除が少ないことから、会社と請負契約を締結し、本人は青色申告の個人事業主として仕事をする人を言います。会社は支払う金額から所得税の源泉控除はしますが、本人は個人事業主として確定申告を行いますと、結構な費用の控除が認められて税金が還付されるという仕組みです。 合法的に割増賃金を少なくするには、変形労働時間制を有効に活用したり、裁量労働制を活用したりすることが有効になる場合があります。また、業務の見直しや、権限の委譲を行い、出勤管理や労働時間管理をできるだけ本人に行わせるようにすることもひとつの有効な方法になりえます。 詳しくは、お問い合わせ下さい。
6月27日に参議院で改正労働基準法が可決成立しました。(施行は10月1日から)改正点は次のとおりです。
1.労働契約期間の上限が3年(専門的知識の必要な職種と60歳以上は5年)になります。(現行は1年と3年)
2.解雇について、「客観的合理的な理由なく、社会通念上相当であると認められない場合は解雇権の濫用になり無効」との条文(18条の2)が追加に されます。
3.解雇予告期間中の退職理由の証明書交付の義務。
4.みなし労働時間制の要件の緩和
企画業務型裁量労働制の用件が緩和。本社部門で経営計画等の重要事項を企画決定する業務に従事する人のみ対象だったものが、支社・工場等でも 経営上重要な部署で導入可能になりました。また、労使委員会の全員の決議が必要だったものが、5分の4以上の賛成で導入が可能になりました。
この場合の労使委員会は、もともと労働基準監督署に設置届けを提出していなければ認められなかったものが、届出の要件がなくなりました。
今回の労働基準法の改正に当たっては、経済団体からの強い要望によって実現したものです。その中で、最も注目されていたのは、「事業主は、従業員を解雇できる。」という条項が原案には入っていましたが、これは労働団体の強い反対にあって削除されました。
しかし、もともと労働契約は民法の規定で解約自由の原則から、事業主に解雇権があると規定されているので、わざわざ労働基準法に規定するべきでないという意見により削除されたもので、今までと大きく違った訳ではありません。
ただ、過去の裁判の判例の積み重ねによって、解雇が非常に制限されているのは事実で、むやみに解雇すると、即、解雇権の濫用と言われてしまいます。
そこで、引き続き経済団体はもう次の改正に向かって運動をしていまして、次なる要点は、「解雇ルール」の規定を定めようとしています。その中でも、注目点は金銭解決のルールをです。
現在、労働基準法には、手続きとして30日分の平均賃金を支払うと即日解雇できる旨定めています。
しかし裁判になった場合、解雇の取り消しの判決が出る場合がほとんどですが、実際に訴えた人が職場に復帰するかといえば、そうでないケースがかなりの数に上ります。事業主側とすれば、いったん解雇した人に戻ってこられると従業員の士気が著しく低下しますし、解雇された従業員もよっぽど性根の座った人でないと、まず勤められないだろうと思います。そこで、裁判になる前に、金銭で解決してしまおうというわけです。
具体的な金額や方法はこれからの審議によりますが、今年中には具体的な案が発表されるということです。
しばらく新聞から目が離せません。また発表されましたら、お知らせいたします。
従来、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用基準が『通常の労働時間の概ね4分の3以上』というあいまいなものから法律の条文に明記される形で、パートに厚生年金の適用基準が変わります(健康保険は現在のところ従来どおり)。
新たな適用基準は、1.週の所定労働時間数が20時間以上、2.年収が65万円以上です。
具体的には、労働時間が1日3時間なら週6日勤務以下、1日4時間なら週5日未満
(5日ちょうどなら適用)、1日5時間なら週4日未満でないと適用になります。また、時給との関係で、1日3時間で週6日勤務の場合でも、723円以上なら65万円を超えてしまいます。
723円×3時間×25日×12ヶ月=65万700円
実際には交通費も含みますので、パートに交通費を支給している事業所ならもっと時給が低くても適用されてしまいます。
では保険料がいくらになるかといえば、1日4時間で週5日勤務、時給800円のケースで計算しますと以下のようになります。(交通費の支給はないものとする)
800円×4時間×22日×12ヶ月=844,800円
844,800円×1000分の135.8÷2=57,361円(事業主負担分のみ)
また、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の適用基準の103万円未満を基準として計算しますと、
1,030,000円×1000分の135.8÷2=69,937円となります。
実際には、標準報酬月額が基準となりますので、ぴったり正確な金額ではありませんが、パート従事者を主力にされている事業所では、実に大きな負担になります。
対策としましては、
1.勤務時間数を基準にして、1日の勤務時間数を減らすか、1週間の勤務日数を減らす必要があります。
2.付帯経費を出来るだけ掛けない
精皆勤手当・交通費などを見直すことが必要です。精皆勤手当は支給しない事業所が多くなっていますし、特に比較的新しい事業所では殆ど支給し ていないことが多いようです。
交通費は勿論必要経費ではありますが、所得税が非課税になっているだけで、給料であることには違いありません。社会保険・労働保険では給料に 含めて保険料の計算をしています。ですから、上限を設けることや、定額とする、あるいは支給しないことも選択肢として考えてもよろしいのではな いでしょうか。
3.時給額を本人の能力などに応じて支給する。
支払う給料を今までより下げますと、労働条件の切り下げになってきますので、ただ保険料の負担がきついからという理由では、切り下げの理由と は認定されません。そこで、人事考課を実施し従業員のやる気と能力に応じて金額を弾力的に運用することが必要になるでしょう。つまり、就業規則 を整備しなおして能力主義を採用することを明記し、それに応じて運用するということです。
パートを補助戦力として見るのではなく、正社員より仕事が出来る人はいくらでもいますので、より積極的に活用していくことが必要でしょう。
4.給与を時間で決定する。
少し乱暴に見えるかもしれない方法ですが、正社員をなくすのもひとつの考え方です。実際にスーパーのような大規模小売業の中には、店長以外 は殆どパートばかりというところもあります。実際の働きに対して時間給の比較がはっきり出てきますから、生産性が上がっている人は、時給が高 く、生産性が低い人は安いということが一目瞭然はっきりします。